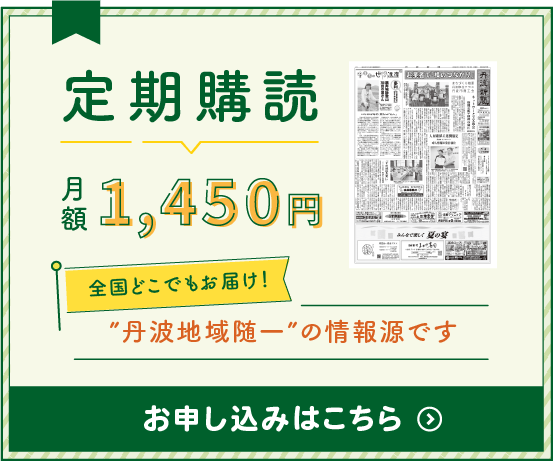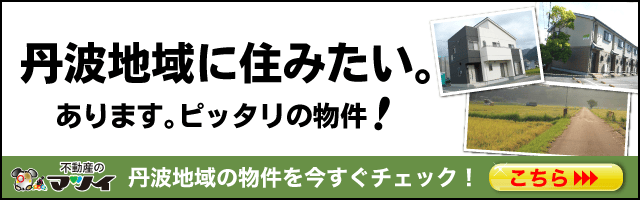2019年12月、中国・武漢で確認され、またたく間に世界中で大流行した新型コロナウイルス感染症。繰り返される大きな感染の波、「緊急事態宣言」などを経て、昨年5月に感染症法上の位置づけが「2類」から「5類」に変更され、季節性インフルエンザなどと同じ扱いになった。5類移行から1年が過ぎた今、兵庫県丹波市においてコロナで変わったこと、変わらなかったこと、元に戻ったことを検証する。
「ここのところは、ぽつ、ぽつ、くらい。落ち着いている」。丹波市医師会事務局の足立宏美さんは、会員から日々届く「COVID―19感染発生届け」を集計し、会員に共有する任務を負っている。最も多かったのが第7波渦中の2022年8月23日。一日で237人を数え、「データ入力にへとへとになった」と振り返る。季節性インフルエンザで経験したことのない人数が続いた。
新型コロナウイルス以前から、同医師会は感染症について、県の発表とは別に市内の流行を監視する独自の報告制度を持っていた。「発生が多い地域や、どの年齢層ではやっているのかが分かり、診療に役立った。情報を持ち寄り共有することの重要性が、今回のコロナ禍で大いに会員に認知されたと思う」と、野上壽彦医師会長は意義を強調する。
開業医では、発熱外来への備えがコロナ前後で変わった。発熱患者は電話をして来院、車の中で待機してもらい、「医院の中に持ち込まれない」よう対策が進んだ。防護服など資材の備えも充実した。以前は咳をする人だけがマスクをしていたが、医療機関や薬局に入るときはマスクを着用するようになった。手指消毒も流行初期ほど熱心ではないが、続いている。感染症を防ぐ行動が習慣づいた市民が一定数いる。
今年3月末まで全額公費で無料接種ができたワクチン。5類に変わった昨年5月9日からの1年の間にも春、秋2回の追加接種があった。
最後の追加接種(昨年9月20日―今年3月31日)の対象者は、「5歳以上で初回接種済み」。4―6回目まで続いた対象者の絞り込みが大幅に緩和され、「ほぼ誰でも打てる」状況だった。しかし、接種した人は1万5212人と、接種率は25・1%(3月末の市人口との比較)だった。
接種が始まった2021年に1回目のワクチンを接種した人は、市人口の79・4%に達していた。市民の間で、感染力は強いものの、弱毒化が言われる新型コロナウイルスへの恐怖心、ワクチンへの関心が薄れていることを如実に裏付けた。
一方、最大回数の7回接種した人が、8495人(65歳以上が8089人、基礎疾患のある12歳―64歳が406人)いた。これらの人にとっては感染防止、かかったときの症状緩和のため、ワクチンは頼みの綱であり続けた。健康で若い人と、高齢者とで新型コロナの認識が異なることを浮き彫りにした。市内の65歳以上高齢者は2万1563人(3月末)。回を追うごとに接種しない高齢者が増え、最終的に接種する人は少数派になり、高齢世代でも恐怖心は薄れた。
5類移行で社会が緩む中、県立丹波医療センターは昨年11月13日まで入院患者の面会禁止を続けた。現在は一部再開。原則家族のみ、一日1回2人までなどと制限が続く。病院入り口の体温を測るサーモカメラは設置したまま。感染が疑わしい人を見つけ出す仕組みを構築し、職員は体調不良時は勤務しない体制が確立、職員自身がもらわない防護技術も進歩した。「持ち込み、持ち込まれ防止」に今も神経をとがらす。社会の「もういいんじゃないか」ムードとの乖離が大きくなっている。
西崎朗院長は新型コロナ感染症を、「私はインフルエンザで亡くなる患者を経験していない。新型コロナはこの冬の10波で亡くなる人が、残念ながら当院でもあった。インフルエンザと一緒にはできない」と、楽観視と一線を画す。院内感染は入院患者の命にかかわりかねず、何としても避けたい。
5類移行後は「医療従事者としての自覚を持って行動をお願いする」と、会食の人数制限などは示していないが、部署ごとの大人数の宴会は今も自粛傾向にある。
感染症が専門の見坂恒明・同病院地域医療教育センター長は、「ロングコビット」と呼ばれる新型コロナ後遺症患者を外来で診ており、厄介さを肌で感じている。若い人でも全身倦怠感、意欲が湧かない、食欲が落ちる、といった症状を訴える。新型コロナ感染症が軽症でも後遺症に悩まされる人がいる。
陰性になるまでの期間を約1日短くする新型コロナ治療薬「ゾコーバ」。5類移行で公費助成がなくなり、5日分の薬代は、窓口負担が2割の人で1万円強。市内の開業医で処方をされるケースは少なく、解熱剤や咳止めが多い。見坂センター長は「少しでもウイルスにさらされる期間を短くした方が後遺症になりにくいと考えられ、自分なら処方を希望する。多くの人にとって、数日安静にしていれば治る病気になってもおり、費用負担と利益を天秤にかけ、判断することになるだろう」と話す。
コロナ禍でも変わらなかったことを西崎院長は「中核病院として診療を続けたこと」と言い、軽症患者を引き受けた丹波篠山市のささやま医療センターとのすみ分けでパンクを免れたと感謝している。一方、コロナ禍の間に、ささやま医療センターと岡本病院が急性期の診療を縮小したため、丹波篠山市からの患者が増えた。2019年の新病院移転年に1700台弱だった救急車の応需が、昨年は3400台にまで増えた。初期研修医を除く常勤医師数はここ数年65人程度で足踏みしており、「医師不足、医師偏在は変わっていない」と危機感を抱いている。