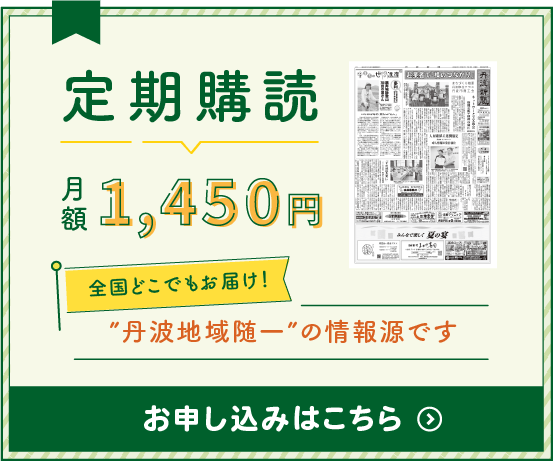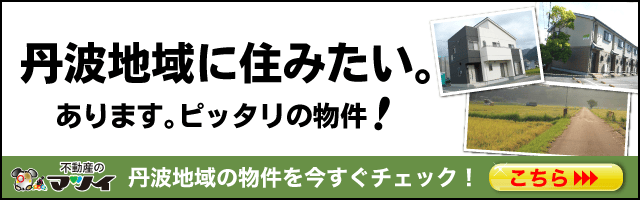2019年12月、中国・武漢で確認され、またたく間に世界中で大流行した新型コロナウイルス感染症。繰り返される大きな感染の波、「緊急事態宣言」などを経て、昨年5月に感染症法上の位置づけが「2類」から「5類」に変更され、季節性インフルエンザなどと同じ扱いになった。5類移行から1年が過ぎた今、兵庫県丹波市においてコロナで変わったこと、変わらなかったこと、元に戻ったことを検証する。
感染リスクの高さから、多くの人が集まる機会を激減させた新型コロナウイルス禍。丹波市民の暮らしには、どのような影響を与えたのか。
◆自治会の書面決議 意図伝わらず苦心
多くの市民から「変わった」と聞かれたのが自治会の運営方法だ。本来は住民が集まり意思決定する総会も、「密」にならないよう、事業案などの承認を書面決議で済ませるケースが多くなった。
市自治会長会の大野亮祐会長(67)は「対面ができないので、意思疎通がスムーズにできなかった。SNS(交流サイト)と同じ」とこぼす。書面では役員の意図が思うように住民に伝わらず、もどかしさを感じた。住民から質問を受けてもスムーズに回答ができず、質問をした住民の家を訪ねたこともあった。
コロナ禍を機に、学校や企業などではウェブ会議アプリなどの情報通信技術(ICT)の活用が進んだ。市や住民らによると、自治会でもごくまれではあるが、会合時にユーチューブや地域の有線放送を活用した例があったという。
だが、大野会長によると、自治会ではICTに不慣れな高齢の役員や、公民館に設備が整っていない所が多く、活用は広まらなかった。感染症法上の位置付けが5類に移行した2023年5月以降は対面での総会が増え始め、現在はほとんどの自治会が対面に戻しているという。
◆継続分かれた催し 知恵出し内容一新
夏や秋の祭りといった自治会主催のイベントも、新型コロナウイルスがまん延していた20―23年春の間は中止を余儀なくされた。また、若手が減り、役員や住民の準備負担が大きかった運動会などの行事はもともと継続が難しい状況にあったため、コロナ禍を機に開催をやめた所も。運動会を、比較的負担の小さい花見に切り替えた所もあったという。
5類移行後は徐々にイベントが再開。しかし、「4年休んでやり方が分からなくなった」と、再開できずにいる自治会もあった。高齢化率が6割を超える同市春日町栢野では、コロナ禍の間に14歳以下の子どもが1人だけになり、秋祭りの伝統「子どもみこし」が途絶えた。
一方、高齢者が集う「いきいき百歳体操」やグラウンドゴルフ大会といった催しは、マスク着用などの感染対策に十分考慮しつつ開催を継続するケースが見られた。
市グラウンド・ゴルフ協会は、会員の意見を踏まえ、年2回の大会を中止することなく続けた。藤原安孝会長(83)は言う。「年を取れば家に引きこもりがちになる。交流することが皆さんの生きがいになっているから」
各地域の住民らが催しを継続するか否かに頭を悩ませる一方で、コロナ禍による4年ぶりの開催を機に、伝統的な運営体制を一新した催しもあった。
同市氷上町成松市街地で行われる夏祭り「愛宕祭」は、呼び物の花火や世相を表す「造り物」などの規模を縮小。「身の丈に合った祭りを」と、住民の労務負担を減らした。
同実行委員会の村上豊委員長(75)は「コロナがなければしんどい中でも続いていたかも。コロナによる空白の期間が、祭を次代につなぐ方法を考え、住民同士で知恵を出し合えるきっかけになった」と、前向きに受け止める。
市島地域の夏の風物詩「川裾まつり」では、運営に参画する自治会数を増やし、各自治会の青年会メンバーを実行委員会の役員に迎え入れ、持続可能な運営体制を構築。若手が縁日ブースを出店するなどし、まつりを盛り上げた。
同まつり実行委員会の坂谷高義委員長(78)は「コロナ禍によって、地域のみんなでまとまることができた。今の若い子はやる気があり、愚痴もこぼさない。このきっかけがなければ、まつりは消滅していたかも」と話す。
◆葬儀の形も変化 家族葬が主流に
葬儀の形も変化している。葬祭業「ルミーナ」(同市青垣町市原)の堀康樹社長(54)によると、コロナ禍前は、自治会が香典受け付けなどの手伝いを担い、近隣住民らを招く一般葬が大半だった。しかし、新型コロナウイルスまん延以降の約2年は、「3密」を避けるために一般葬がほぼなくなり、家族葬が大半を占めた。5類に移行し、新型コロナ禍が収束した現在も家族葬が8割ほどで、主流になっているという。
堀社長は「喪主の方に、参列した高齢の方にコロナがうつるなどして『周りに迷惑をかけてはいけない』という気持ちがあり、一般葬を迷われているのでは」と推察。現在も葬儀会場ではマスクを着用している人が多いという。
取材先で「コロナ禍の暮らしで変わらなかったものは」と問うと、皆が一様に「うーん」と答えを詰まらせた。「変わったものしかないんちゃうか」という声も聞かれた。市民の暮らしを一変させた未曾有のウイルスは、少子高齢化が進む地域が従来から抱えていた課題を浮き彫りにし、それを解決するための手法を見直す契機を与えた。