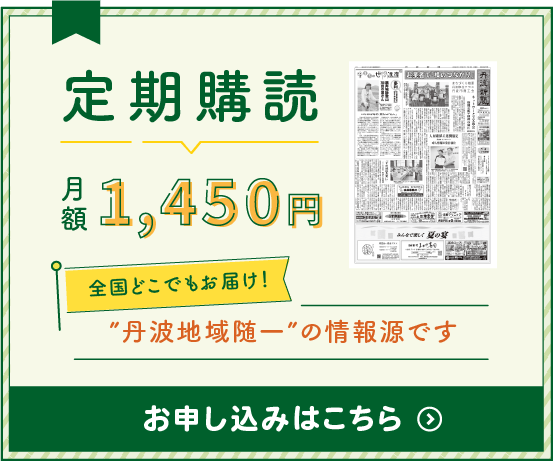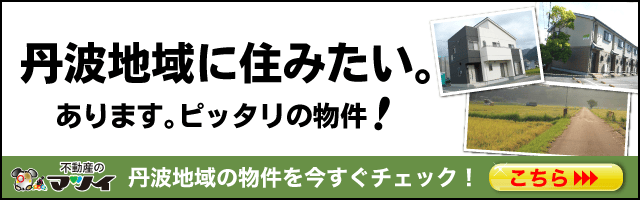鳥獣害対策の将来を担う若者や関心のある市民がその現状や対策を学び、課題解決に取り組む「獣がい対策実践塾」(兵庫県丹波篠山市主催)が今月、同市のみたけ会館で開講した。学生や都市住民、非農家ら、これまで獣害と直接関わりがない人も交えて、現場実習を通して学ぶ連続講座で、NPO法人・里地里山問題研究所(さともん)の代表理事、鈴木克哉さん(48)を講師に2018年度から開いている。今年度は5回の講座を予定し、市民6人と篠山産業、篠山東雲両高校の生徒計14人が受講。初回は、獣害の現状と、なぜ獣害が起こるのかなどについて講義を受けた。
鈴木さんによると、農作物の被害額は全国で156億円(2022年度)、市内では1166万円(昨年度)だった。ただ、自家用作物の被害額が含まれておらず、金額には表せない被害があると指摘。以前と比べ数字では被害額は下がっているものの現場感覚では落ち着いていないことについては、対策が浸透している以上に、獣害によるモチベーション低下や高齢化による離農で作付け面積が減少しているためとした。
深刻化している原因は、森林破壊や山に餌がないことではなく、「里の餌が山の餌よりはるかに魅力的であることを野生動物に知られてしまったから」とし、適切な対策を取らないと野生動物を繰り返し集落に呼び込むことになるとした。
地域が取り組む獣害対策に、▽防護柵を適切に設置▽「被害と感じない」誘引物(放任果樹や収穫残渣など)の管理▽山裾のやぶを切り払うなど出没しづらい環境整備▽追い払い▽出没個体を捕獲―などを挙げた。
また、電気柵の有効性を伝える中で、サルの学習能力の高さを利用した通電支柱とワイヤメッシュを組み合わせた防護柵「おじろ用心棒」を紹介したほか、カラス対策には黒色のテグス糸を2メートル間隔で格子状に張ることが有効などと解説。一方、光や音(超音波)、臭い(オオカミの尿など)で撃退をうたった商品やピンク色のテープは「効果なし」とした。
人口減少、高齢化により、地域主体で継続的に取り組む人手が不足していることも課題に挙げた。解決策として、獣害対策活動をきっかけに特定地域への愛着や関わりを深めながら地域課題の解決や活性化に多様な形で関わり、貢献する「関係人口」の創出・拡大を図る仕組みづくりが必要とし、さともんが展開している黒豆オーナーや川阪オープンフィールドの取り組みを紹介した。
12月8日まで、おじろ用心棒の設置実習や獣害防護柵の点検、サル探索や竹林整備などによる野生動物の潜み場をなくす作業、ジビエ料理などのプログラムを体験する。