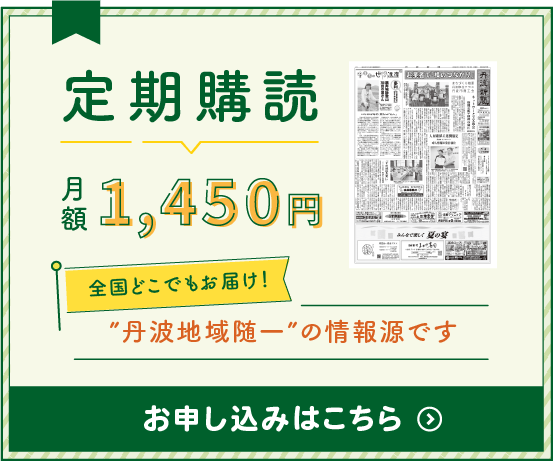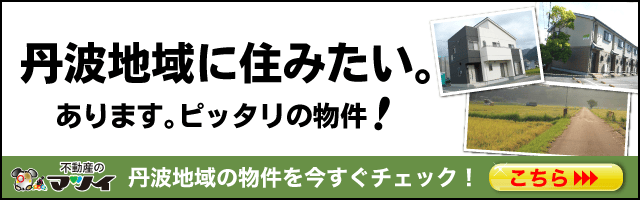兵庫県丹波市氷上町谷村のまつもと医院は4月から、5―16歳を対象とした発達検査を院内で実施する。長年、子どもの発達支援教育に専門的に携わっている松本緑さん(62)と、夫で小児科医の松本好弘院長(72)が、新たな事業として発達支援に力を入れ、医療、療育、教育の連携を目指していく。
発達検査は、世界各地で使われている児童用知能検査「WISC(ウィスク)」の最新版「WISC―V(ファイブ)」を用いて公認心理士が行い、松本院長が診断する。指標となる▽言語理解▽視空間▽流動性推理▽ワーキングメモリー▽処理速度―の5つを数値で算出するもので、平均と比べて、どの部分の能力が突出しているかを数字で把握できるため、個人に合った関わり方につなげやすいという。
「まずは、特性を正しく理解することが大事」と緑さん。合わない指導で失敗体験が積み重なり、自信を無くしていくケースもあるといい、「最終的な目標は、その人らしく自立できること。医療、療育、教育をうまくつなげて、社会性を育みたい」と話す。保護者や教職員への研修や専門家による個別相談会なども行っていく予定。
緑さんは、臨床心理学を深く学び、二十数年前に発達支援教育を専門とする「さくらこどもセンター」を同県三田市で立ち上げた。現在は、同県丹波篠山市今田町下小野原の「エリクソン校」と2カ所で放課後デイサービスと未就学児の発達支援事業を行う。また、株式会社「La luche(ラ・ルーシュ)」(神戸市)を創業し、教材の普及やオンラインでの支援サービスを行っている。
松本院長は3年前に脳出血、1年半前に脳こうそくを患い、昨年8月に退院後、診療日をしぼって再開を決意。その際、夫婦で話し合い、「いろいろな人が集える場に」と、待合室を多目的スペースにも使えるよう改装するなどした。
二人は「医院としては診療日が減り、残念なことではあるが、子どもたちのために二人で新しいことを始められるという思いもある。病気の人に限らず、地域の人が支え合える場になれれば」と話している。
発達検査費用は保険が適用される。所見作成費4000円が必要。同医院インスタグラムで診療日を知らせている。
「この子のために」
緑さんが発達教育を専門的に学んだきっかけは、親代わりに育てることになった当時8歳の甥が、自閉スペクトラム症だったことだった。実の兄が若くして病気で亡くなり、3人の子どもを松本家に迎えることに。背中を押したのは、松本院長の「もし子どもたちを引き取らないのなら、医者を辞める」との言葉だった。3人の実子と合わせて、6人の子育てが始まった。
「この子をどう育てたらいいんだろう」。カウンセラーをしていた緑さんは、悩み、駆け回った末、児童精神科医の佐々木正美さんと出会って光を見出した。自閉スペクトラム症を対象としたプログラム「TEACCH(ティーチ)」を国内外で学び、甥に実践する中で、「何という豊かな世界を持っている子だったのか」と気づかされたという。 甥は今、岐阜県で86歳の祖母と2人で暮らし、郵便局に勤めている。大学は京都の南禅寺で手伝いをしながら通ったという。「本当に優しい、素敵な子」と緑さん。「正しい関わり方で子どもたちがどんどん力を伸ばしていく姿を見てきた。これからは20年間で培ったメソッドを伝えていきたい」と話している。