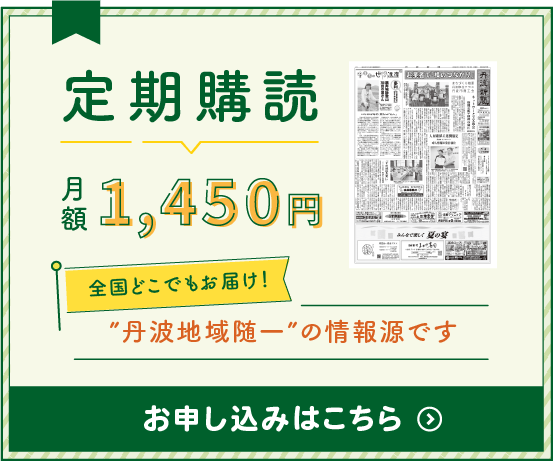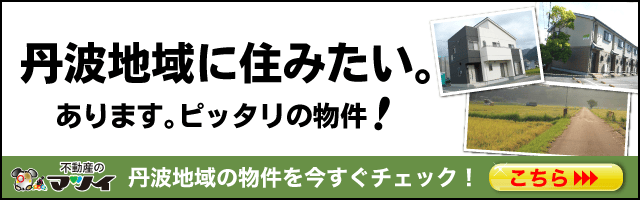兵庫陶芸美術館(兵庫県丹波篠山市今田町上立杭)は、開館20周年を記念した特別展「東山焼と姫路のやきもの」を同館(今田町上立杭)で開催している。東山焼、永世舎、鷺脚焼など、近世後期から近代に花開いた姫路のやきものを、約170点の作品を通して紹介している。開館は午前10時―午後5時。5月25日まで。月曜休館(5月5日は開館、7日休館)。
東山焼は1822年(文政5)、姫路城の南東に位置する興禅寺山東麓(姫路市東山)で始まった。当時、高級ブランド品だった京焼から最新デザインを、一大生産地の肥前有田(佐賀県)から窯業技術を取り入れ、作品は青磁や染付を中心に磁器から陶器まで多岐にわたる。興禅寺山窯では青磁と染付を中心に焼造された。姫路城の西に移った男山窯では染付が主に焼かれ、中でも古染付写しや祥瑞写しなどの染付に優品が多く見られ、明治時代まで作り続けられた。
東山焼は、器面に繊細な筆致で山水や幾何学模様が描かれた染付に加え、翡翠を思わせる淡い青緑色の青磁が特徴的。同展では、各地の美術館や博物館、個人が大切に伝えてきた多種多様な優品が一堂に会している。
窯業所の永世舎は1877年(明治10)、士族救済の目的で大蔵前町(現・塩町―十二所前町)に設立された。華やかな色絵や鮮やかな青釉が特徴的で、主に輸出用の色絵製品が作られ、88年(明治21)頃まで操業。明治時代前期に欧米諸国や国内で開催された万国博覧会や内国勧業博覧会に向けて、明治政府が作成した図案集「温知図録」に掲載されている形や模様などを模した作品が数多く見られる。
永世舎の陶工・中川勇次郎(1849―1922年)が1881年(明治14)に創業した鷺脚焼は、精緻な竹べら細工が特徴的で、土味が残る急須や碗、香合などが知られる。同展では東山焼や永世舎とは趣の異なるやきものの魅力を紹介している。
観覧料は一般1200円、高校生以下無料。