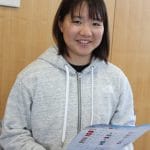今年で終戦から78年が経過した。戦争を体験した人や、その遺族の多くが高齢化、もしくは亡くなる中、丹波新聞社の呼びかけに対し、その経験を次世代に語り継ごうと応じていただいた人たちの、戦争の記憶をたどる。今回は荻野早苗さん(84)=兵庫県丹波市春日町山田=。
4人きょうだいの長女として、兵庫県庁で働いていた父の大蔵さんと、母の家野さんの間に生まれた。戦況が悪化し、大蔵さんは戦地へ赴いた。一家の大黒柱がいなくなり、家野さんの実家がある同市山南町池谷で暮らすことになった。
ほどなくして、一緒に池谷で暮らしていた家野さんの弟、音治さんのもとに赤紙が届いた。地元の谷川駅から出征する日、「おいちゃん」と呼んでいた音治さんから「大きくなれよ」と声をかけられた。「父と母には『もう帰ってこられないかも』『行ってまいります』と言っていた。ひるむことなく、『きりっ』としていた姿が小さいなりに忘れられない」
汽車の中は出征する兵士たちであふれていた。沿道を埋め尽くす大衆は「万歳」と言いながら、両手に持つ日本国旗の小旗を振った。子どもながらに「にぎやかなこっちゃ。お祭り騒ぎ」と感じたという。
後日、家にボルネオ島から、音治さんの戦死の一報が届いた。祖母と家野さんははがきをじっと読み、「お国のために死んでしまった」と泣いた。きれいな白い袋に入り、「遺骨」として届いた箱の中には、現地から採取したと思われる砂や小石のようなものが入っていた。祖母は「音治がこんな姿になった」と、また泣いた。
食事は質素な毎日だった。家で育てた米は供出。食べられる米は細い「支那米」だった。雑炊にはサツマイモなどの野菜を入れ、「水の方が多いぐらい、かさをまして」炊いた。ツクシやイナゴ、イタドリ、魚など、野辺や山、川からとったものが貴重な食料だった。それでも「味がどうこうではない。食べられたらそれだけで幸せだった」と振り返る。
家は男手が少なかったので、きょうだいは親の苦労を察し、言われるでもなく農作業を手伝っていた。家野さんは自分の着物を裁断し、子どもたちの服に仕立て直した。「きょうだいで勉強をしていると、何も言わず、後ろから『ちょんちょん』と頭をなでてくれた。不自由だったが、母から愚痴は一言も聞いたことはなかったし、温もりを感じていた。愛情豊かに育てられた」
戦後、池谷の家に避難していた親戚が大阪に帰ることになり、家野さんと共に大阪・鶴橋へ様子を見に行った。「一面ぼこぼこで、焼け野原」。無残な光景が、今でも忘れられない。
大蔵さんは戦地から帰還したが結核を患い、戦後まもなくして逝去。弟は栄養失調でこの世を去った。祖父母と家野さんは、家の家財や服を売りながら生計を立て、3人の娘を育てた。
早苗さんは38年間、小学校教師として丹波市内の小学校で勤め上げた。
「当時は家族という集団で『心のやり取り』をしていた。そこから人をいつくしむ気持ちが生まれていた」と語る。「戦争で多くの尊い命は奪われ、国中が貧困の生活に一変した。悲惨さを忘れず、命を大切にする社会が続くように」と切に願う。